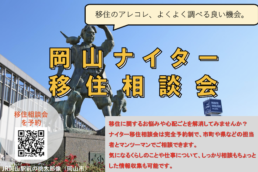お試し協力隊レポート|村瀬司さん
真庭滞在記
こんにちは。
2025年9月3日から9月5日まで、真庭市のお試し協力隊に参加させていただきました「村瀬司」と申します。
私は大学4年生で、卒業論文の調査先が真庭市であり、真庭市に滞在する予定がありました。
その中で、真庭市そのものの理解を深めたいことや、将来を見据えた際の一つのライフプランの構築の参考になればと思い、お試し協力隊に参加させていただく次第となりました。
本記事では、私が訪れた真庭市のスポット、協力隊会議に参加した様子、現在真庭市で積極的に導入が進んでいるスマートストアの来訪記録などを、時系列順で掲載されていただきます。
1日目:真庭市巡り
初日は交流定住センターの矢作さんの案内で、真庭市内をぐるっと巡りました。
訪れた場所を以下に記します。

◆神庭の滝
前日に発生したゲリラ豪雨の影響により、通常よりも水量が多く、迫力を感じられる状況でした。
周囲は非常に涼しい環境であり、自然を十分に堪能することができました。
なお、写真には記録していませんが、入口付近には猿がいました。
この辺りには猿に関する研究施設もあるなど、猿の生態を見るには良さそうな場所みたいです。

本を読むだけでなく、子ども用スペースやイベントの告知など、地域のたまり場としての役割を実感することができました。
真庭市に関する書籍も存在し、特に食に関する文献が目を引きました。
お試し協力隊の期間終了後にも立ち寄る機会があったのですが、日曜日だったからか、地域住民の方々や学生でにぎわいを見せていました。
快適に読書に没頭できたので、また機会があればぜひ来訪したいと思います。

まず、御前酒蔵元辻本店を訪れました。
試飲した日本酒は比較的甘めのものが多く、飲みなれていない人でもおいしく飲めると感じました。
昼食はCAFE indigo blueさんへお邪魔しました。
2種のあいがけカレーをいただきましたが、コクがありつつもスパイスが効いていてとてもおいしかったです。
お店のレジの裏では、自ら製作されたという革製品が販売されていました。
勝山町並み保存地区は、真庭への移住者の方々が多く店を出されているとのことで、平日の昼間でしたが活気を感じました。
新庄村から蒜山につながる長いトンネルを抜け、蒜山に入ってすぐのところに忽然と現れたカフェは趣のある雰囲気で、そこにいるだけでも満足感が高かったです。
自家製ジンジャーエールをいただきましたが、今まで飲んだジンジャーエールの中で最も美味しかったです。
店の外には某アニメのどこでも行けそうなドアがあったり、好奇心をくすぐってくれるような仕掛けも多くありました。

予定にはなかったのですが、会長の植木様と1時間ほどお話ができました。
山ぶどうから作るワインの生産にかける思いや、山ぶどうワインに対する世間の逆境をどう乗り越えていったかなど、貴重なお話を聞くことができ、非常に有意義な時間でした。
山ぶどうからワインを作ることについて、イチから作り上げて評価されたのは、絶え間ない努力と、それを支えた方々の賜物であると実感することができました。
今回は、山ぶどうで作られたジュースを試飲しましたが、酸っぱさのなかに旨みや甘みがあり、奥の深いジュースでした。
湯原地域では、オオサンショウウオを見ることができるようです。
ちなみに、ここではオオサンショウウオのことを「はんざき」と呼称するそうです。
泉質はアルカリ性の、いわゆる美肌の湯とよばれるもので、温泉好きからの評価も高いようです。
実際、私も多くの温泉に入浴してきましたが、好みの泉質で絶対に今度プライベートで来ようと誓いました。
入浴は「下湯原温泉 ひまわり館」に入りました。
露天風呂のみで、非常に解放感がありました。
ここは地元の方が良く来訪される場所だそうで、この日も地元の方々が5名程度いらっしゃいました。
◆真庭市交流定住センター 矢作さんとのお話
一日目の活動の中で真庭市交流定住センターの矢作さんと興味深い話ができたので、特に印象に残ったことを抜粋しつつ、感じたことを述べたいと思います。
「里山資本主義であるような、従来の資本活動の他に、自ら生産の立場に立ったり、生産に関わる方々とつながることは重要。」といった発言では、都会的な消費社会だけでなく、生産活動そのものにもっと目を向けていくことで、それが価値を生み出していくと解釈しました。
「真庭地域は、様々なことに挑戦している方が多くいて、トライアンドエラーができる環境であると思う。」というお話では、地域おこし協力隊だけでなく、地域に住んでいる様々な人が何かに挑戦していて、それを受け入れる土壌が整っていると推察できました。
また、「真庭には平日は会社員(役所)として働き、週末は農業をしている人が多くいて、バイタリティが尋常ではないと感じた。」というお話では、農業や会社員としての務めにやりがいや意義を感じているからこそ、それが苦にならずに続けていけるのだと感じました。
その中で、様々なことにチャレンジしていくには、それを考え実行できる余白が必要であるのではないかと思いました。
様々なことにチャレンジしている人は、それを楽しんでやっているからこそ、継続できている、すなわち、余白を作れているのではないかと思います。
◆1日目の感想
真庭市をほぼ一周して思ったことは、とにかく広いことでした。
同じ市域でも車で1時間以上かかることがざらにあり、広大であることを実感できました。
昔は地域ごとに自治体が違ったためか、エリアごとに集落や景勝地の特徴があって興味深かったです。
車内から景色を見ていたときに、水力発電所やダム、温泉地が多くあり、卓越した水資源に支えられていることが伺えました。
この一日で様々な方々と出会うことができましたが、皆さんが自らの夢や目標に向かって様々な活用をされており、それが真庭市の活力につながっていると実感することができました。
2日目:協力隊会議・地域おこし協力隊について
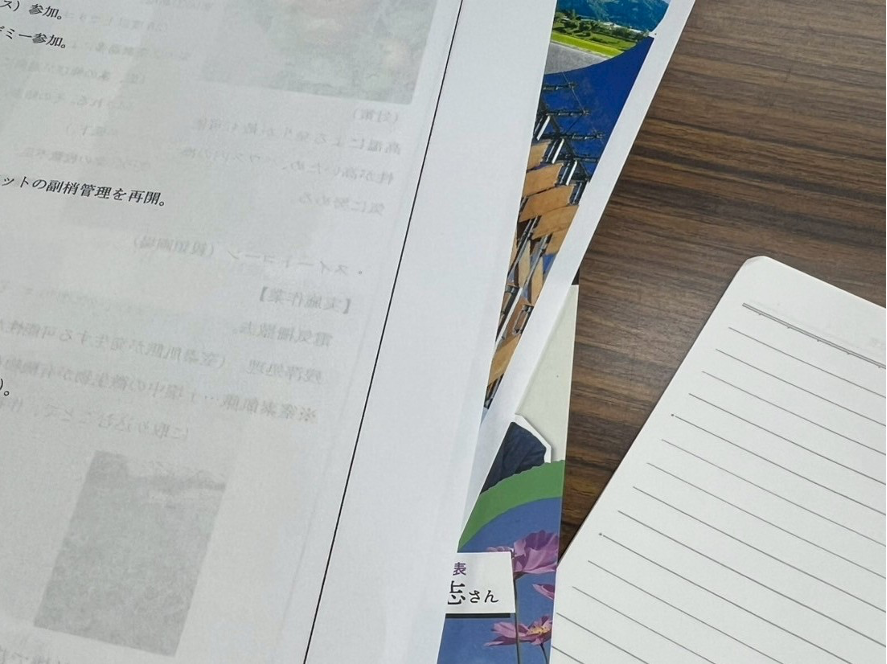
◆協力隊会議に参加して
協力隊会議とは、月に2回、地域おこし協力隊や市役所の担当職員、地域住民の方々が集って、協力隊の活動報告や今後の方向性などを確認する場です。
会議では、時には鋭い意見が飛び交い、活発で意義のある意見交換の場になっていると感じました。
地域おこし協力隊が一丸となって、地域を発展させるという意思が垣間見えた瞬間でした。
地域おこし協力隊の中だけでなく、市役所の方々も会議に参加されることで、様々な立場からの意見を拾うことができ、改善に大いに役立つ仕組みが構築されていました。
一人ひとりが柔軟にやりたい分野を選択でき、スペシャリストとして成長できる環境が整っていると感じました。
また、会議の雰囲気は、わきあいあいとしていたことが印象的でした。
この雰囲気が継続されているからこそ、地域おこし協力隊がのびのびと活動できていると感じました。
◆協力隊についてのお話
午後からは、地域おこし協力隊の実情や今後の展望について、協力隊の庄司さんにお話を伺うことができました。
この項では、その中で特に印象に残ったことをまとめ、その中で私が思ったことを記します。
「地域おこし協力隊は業務内容が一人ひとり違うため、一体感が生まれにくい。そのため苦労をお互い理解しにくく、ギャップ埋めづらい。」というお話では、真庭市の地域おこし協力隊はこのようなギャップをできるかぎり埋めるべく、協力隊会議などを通じてギャップの是正に取り組んでおり、会議の後は、参加したメンバーで食事をするなどして親睦を図る機会もあり、その場で相談できるような環境を整えることも重要であると感じました。
「地域おこし協力隊は自分でしたいことを決めて活動することができる分、自らを律することができる人間にしか務まらないと思う」というお話では、地域に資するという目的を見失わずに、自らが活動を楽しむことによって、自ずと自律が促進されるのではないかと思います。
これは地域おこし協力隊に限らず、学生の私にも刺さる内容であり、何かを成し遂げる際に、目的を見失うことなく楽しみを見出すことを目指していこうと強く思った瞬間でした。
「地域おこし協力隊に対するイメージとして。広告をしていく最中で齟齬や錯覚が起こり、本来とは違う姿で伝わることがある」という発言では、世間で広がる地域おこし協力隊に対するイメージの乖離についての原因として、広告という抽出された情報が先行して、本来の姿が想像できなくなっていることを示唆しているのではないかと思いました。
本来の姿を知ってもらうには、お試し協力隊などの施策や、それに参加した者の積極的な発信が重要であるように思いました。
私もお試し協力隊に参加した者として、少しでも地域おこし協力隊のことを伝えることができるよう貢献したいです。
◆2日目の感想
地域おこし協力隊について、参加前は広告等を見て、「一丸となって地域課題に取り組む」というイメージを抱いていました。
しかし、実際には一人ひとりが自ら設定した目標に真摯に取り組んでいる姿勢を知って、意外に感じる面もありました。
また、地域おこし協力隊を統括するにあたり、一般の企業と同様に折衝や人との関わりが存在する点に共通性を見出すことは、今後も重要な要素であると感じました。
加えて、一人ひとりが業務に熱中しているからこそ、内部でしっかりと意見を交わし合える関係性が欠かせないのだと学ぶことができました。
さらに、会議や庄司さんのお話を通じて、真庭という地域に強い愛着を持ち、そこで懸命に活躍している姿を拝見したことで、地域貢献の尊さを実感することができました。
このお話を伺い、生産という営みそのものが非常に重要であり、今後も守り続けていかなければならないものであると強く感じました。
3日目:スマートストア見学
スマートストアとは、スマートフォンなど、デジタル技術を活用した無人の店舗です。
真庭市では、吉縁起村での導入を皮切りに、展開が進んでいます。
真庭市内のスマートストアの場所は以下の通りです。
◆なぜスマートストアが始まったのか
人口減少が続く地域では、商店の撤退が続き、地域住民が気軽に物資を調達することが難しくなっています。
そこで、無人店舗にすることで経費削減を図りつつ、住民の物資調達を円滑に行うことができるよう始まったものです。
◆スマートストア来訪記録:中国勝山駅
取扱品目:飲料、お菓子、文房具、お土産
客層:学生、観光客
防犯面:駅の中にあるので、人の出入りなどは把握しやすい



◆スマートストア来訪記録:真庭市役所
取扱品目:お菓子、生活用品、地物
客層:市役所の職員さん
防犯面:市役所内の奥にある。常に電気はついている



◆スマートストア来訪記録:白梅総合体育館
取扱品目:飲料、お菓子、運動用グッズ
客層:体育館利用者
防犯面:暗い



◆スマートストア来訪記録:吉縁起村
取扱品目:吉縁起村で企画した商品、飲料など
客層:地域住民、観光客
防犯面:防犯カメラあり。大きな道路沿いのため人目につく立地
備考:7月に追突事故があった影響で、来訪時点(9月8日)では一部商品の取り扱いがありませんでした。修繕が完了次第品目を増やすそうです。

◆3日目の感想
白梅総合体育館、真庭市役所、中国勝山駅にあるストアについては、客層を絞り込み、スポット的な商品供給を行っている印象を受けました。
防犯面に関しては、中国勝山駅と市役所はいずれも施設内の人の目が届く場所に所在しているため、窃盗等の被害は少ないのではないかと感じました。
一方で、白梅総合体育館は一見分かりにくい場所に位置し、店舗に入るまでは暗所であることから、やや立ち入りづらい雰囲気があるように思いました。
来訪時には利用客の姿は見受けられませんでしたが、局所的な時間帯での利用が想定されているものと考えられます。
一方で、いざというときにあると助かるものや、不足すると困るものを提供できる点は、各地のニーズに応じた柔軟な出店形態の大きな利点であると感じました。
さらに、大規模な購買を前提としないことから、在庫管理の簡略化にも資する形態であると学びました。
全体のまとめ
3日間の活動を通じてまず感じたのは、真庭市には多方面で活動される移住者の方々や、その取り組みを理解し協力される熱意ある住民の方々が多いという点です。
イベントの開催や事業の立ち上げにおいては失敗も生じますが、それを振り返り再挑戦できる土壌があるという風に感じました。
また、多方面で活動するためには、活動に充てる時間や気力といった「余白」が必要であり、真庭の方々は生活の中でその余白を確保し、活動へのモチベーションにつなげていると感じました。
次に、地域おこし協力隊については、真庭市においては地域おこしの主役はあくまで住民であり、協力隊はその取り組みに協力する立場であることを学びました。
以前は協力隊が主導的に活動しているイメージを持っていましたが、ここにイメージの相違を感じました。
また、協力隊の統括においては、一人ひとりが独立した活動を行っているからこそ、協力隊同士で意見を交わし合える関係性の構築が重要であるというお話を伺い、これは協力隊に限らず一般社会においても目指すべき一つのモデルであると考えました。
さらに、3日間の活動の中で、真庭市でご活躍されている方々のお話を伺う機会が多くありましたが、共通していたのは「いかにして自らが真庭に貢献できるか」を真剣に思案されている点でした。
方向性や事業内容には違いがあっても、「地域にどう貢献できるか」という思いが共通しており、街全体が同じ方向を向いているように感じました。
また、地域おこし協力隊に従事されている方々にお話を伺うと、人生設計を変更して真庭に来られた方や、田舎暮らしを希望して移住された方など理由は様々でしたが、多くの方が「真庭に来て良かった」と語っておられました。
そのお言葉から、真庭への感謝と愛着が、地域に貢献したいという強い思いにつながっているのだと感じました。